早生まれの子どもは、同学年の中でどうしても発達が遅れがちです。その差は「ただの個性」で片づけられず、集団生活の中で劣等感を抱きやすく、自己肯定感の低下につながります。放っておけば「自分はできない子」という意識が根付いてしまう危険さえあります。だからこそ、早生まれの子には意識的に習い事などの新しい環境を与えることが必要です。本記事では、筆者の体験談を交えながら、なぜ早生まれに習い事が有効なのかを解説します。早生まれで悩んでいる親御さんは、ぜひ参考にしてください。
習い事が早生まれの子に効果的な理由
早生まれの子は集団生活の中で「いつも下に見られる立場」になりやすく、そのままにしておくと劣等感が子供の中で定着してしまいます。だからこそ、習い事で環境を変えることが重要です。習い事には以下のような効果があります。
- 学年に縛られない集団に入れる
- 年下の子と関わることで「お兄さん・お姉さん」としての立場を経験できる
- 新しい環境で「できた!」という成功体験を積みやすい
- 学びの場が広がり、自信につながる
特に大切なのは「年下と関わる経験」です。普段は常に“クラスで一番幼い立場”で過ごしている早生まれの子も、年下の子と一緒なら「自分の方ができる」と実感できます。この体験が自己肯定感を押し上げ、劣等感を和らげる大きなきっかけになります。
我が家の体験談|息子が英語を習って変わったこと
私の息子は週1回、保育園の後に英語を習っています。教室には年下の子や、まだ保育園にも通っていない子も多く、なかには親と離れるだけで大泣きする子もいます。そんな中、保育園生活で親と離れることに慣れている息子は、落ち着いて授業に参加できています。それだけでも「自分はできる」という自信につながり、親としても成長を強く感じました。
さらに、授業で学んだことを家で話してくれるようになり、英語に関しては保育園よりも主体的に取り組んでいる様子が見えます。実際、保育園には「行きたくない」と泣く日があっても、英語教室には「行きたい」と自分から言うほど。明らかに笑顔の数も増え、楽しそうに通っています。
正直に言えば、もし英語を習わせていなければ、息子が「お兄さんとしての立場を経験する場」も「できた!」と胸を張れる機会も少なかったと思います。早生まれだからこそ、こうした環境を意識的に与えることが、自己肯定感を高めるために欠かせないのだと実感しています。
早生まれの子におすすめの習い事の選び方
早生まれの子には、とにかく自己肯定感を高められる習い事を選ぶことが欠かせません。間違った選び方をすると、劣等感を助長するだけで時間もお金も無駄になります。具体的には、以下のポイントを意識してください。
- 学年に縛られない習い事(英語・音楽・体操など)
年下の子が混ざるコミュニティは特に効果的です。常に“下の立場”で過ごしている子に「上の立場」を経験させることはとてもおすすめです。- 成長スピードに合わせてくれる先生がいるか
一律に進める集団指導では早生まれの子はついていけず、劣等感を積み重ねます。少人数制やマンツーマン指導の習い事を優先しましょう。- 子どもが心から楽しめるかどうか
結局これが最も大事です。興味がない習い事を無理に続けさせても意味がありません。親の見栄や自己満足で選んだ習い事ほど失敗します。
逆に、年上ばかりの集団や競争の激しい習い事は、幼少期の早生まれの子には不向きです。成長の遅れがはっきり表れ、子どもに「やっぱり自分はできない」という意識を植えつけるだけになります。
まとめ|早生まれだからこそ習い事で自信をつけよう
早生まれの子は、放っておけば劣等感を抱いたまま成長しやすく、自己肯定感が低いまま小学校に上がる危険があります。しかし、習い事で環境を変えれば、その流れを断ち切ることができます。特に英語のように年齢差が出にくく、成功体験を積みやすい習い事は有効です。
ただし「何でもやらせればいい」わけではありません。親が体験レッスンなどを通して、子どもに合った場を見極める責任があります。見極めを怠れば、せっかくの習い事が無駄になるどころか逆効果になることもあるのです。
正しい習い事に出会えれば、それはやがて同級生をも上回る自信と力になり、子どもは「自分はできる」と胸を張れるようになります。早生まれだからこそ、親が環境を整え、武器を与えてあげる必要があるのです。

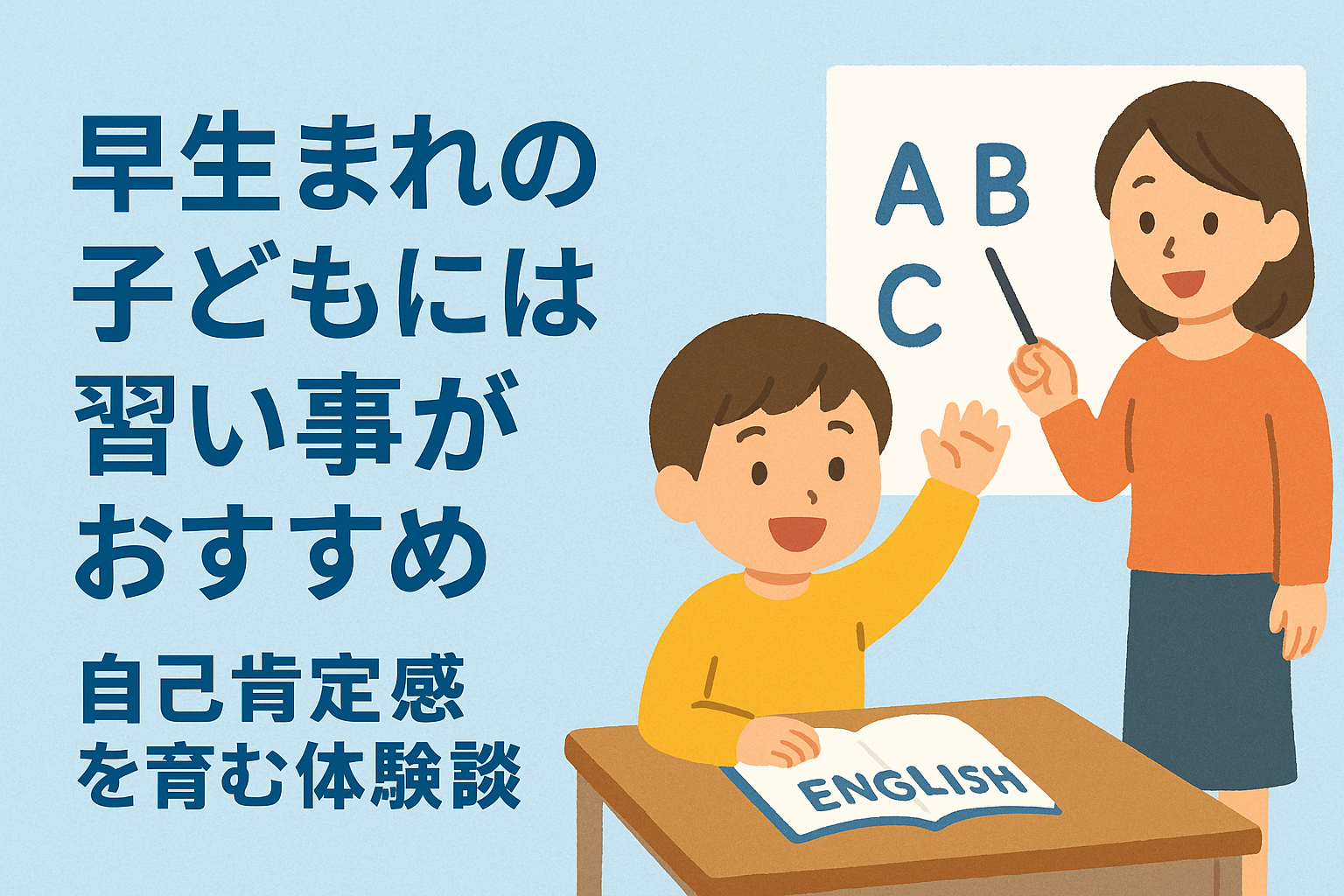

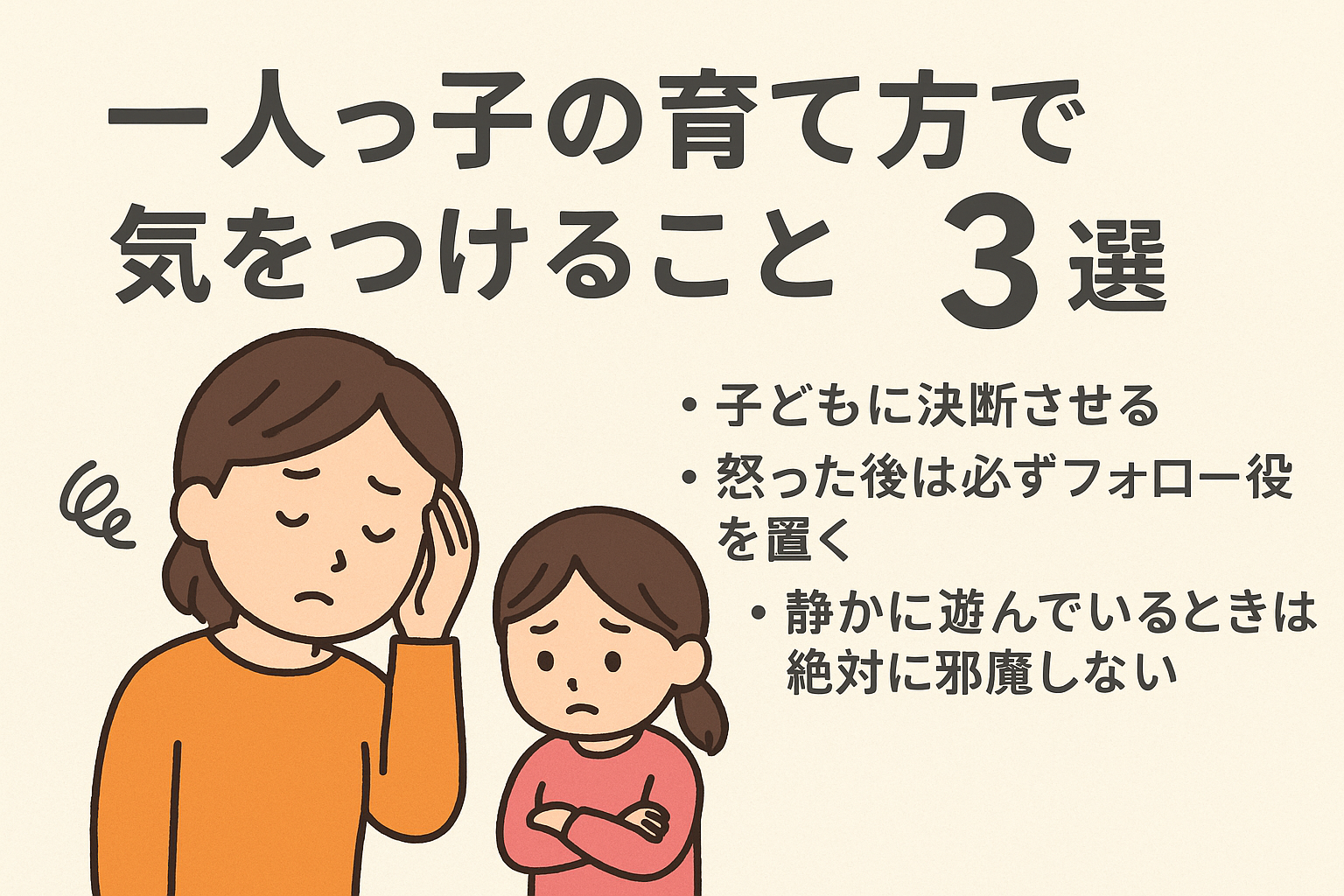
コメント