早生まれの子どもを育てる親の多くが、「どうしても不利なんじゃないか」と不安を抱えています。実際に、東大生の誕生月の統計を見ると、4月~6月生まれが圧倒的に多く、1月~3月生まれは少数派。これは単なる偶然ではありません。
確かに発達の遅れは10歳を超えれば目立たなくなります。しかし問題はそこまでの幼少期です。幼いころから周囲と比べられ続け、劣等感を植えつけられた子どもは、「自分はダメだ」という思い込みを抱いたまま成長してしまいます。その自己否定こそが、学力や挑戦心の差となってもっと自己嫌悪に陥るのです。
つまり、早生まれが不利かどうかは生まれ月そのものではなく、親の育て方次第で決まるということ。放っておけば子どもは自信を失い続けますが、正しく関われば強みを伸ばし、大きく成長できます。
そこで今回は、早生まれの子を持つ親が絶対に知っておくべき育て方について紹介していきます。
大前提|早生まれには確かにメリットがある
「早生まれ=不利」と思い込むのは間違いです。確かに発達の差で苦労はしますが、その一方で 早生まれだからこそ得られるメリットも数多く存在します。
- 脳が若いうちから教育を受けられる
- 遅生まれの子から刺激をもらえる環境にある
こうしたプラス要素を無視して、劣等感ばかりにとらわれているのは親の思い込みです。
むしろ、早生まれの子を育てる親が最初にやるべきことは、ネガティブな側面ばかりを見るのではなく、事実として存在するメリットをきちんと理解すること。
ここを押さえておかないと、子どもにまで「自分は不利なんだ」という間違った刷り込みをしてしまいます。
詳しいメリットについてはこちらにまとめています。
【関連記事】
(内部リンク) 【実体験あり】早生まれのメリット5選!劣等感で悩んでいるあなたへ! – テツパパのおでかけ日和
早生まれの子が感じやすい「劣等感」
・日本の教育制度によりスタートから不利になる
日本の学校教育は4月始まり。つまり、4月生まれと翌年3月生まれでは最大で1年近い差があります。早生まれの子は心身ともに未発達のまま同じ土俵に立たされるため、どうしても「周りはできるのに自分はできない」という経験を積みやすく、スタート時点から劣等感を抱えやすいのです。
・大人から見れば小さな差でも、子どもにとっては致命的な差
「たかが数か月の違い」と片づけるのは大人の視点にすぎません。幼少期の数か月は、体格、運動能力、言語発達のすべてに大きな差を生みます。足の速さ、背の高さ、言葉の発達。どれを取っても早生まれの子は不利な状況からスタートします。
・繰り返される“できない経験”が「自分はダメだ」という思い込みにつながる
友達はできるのに、自分はできない。そんな場面に何度も直面するうちに、子どもは「自分は劣っている」「ダメな子なんだ」と思い込んでしまいます。この自己否定の積み重ねこそが、将来にわたって自己肯定感を下げる大きな要因になります。
親の早生まれっ子の育て方4選
早生まれの子は、劣等感を抱えやすいのが現実です。「自分はダメな子だ」と思い込んだまま成長してしまえば、小学校・中学校、そしてその先の人生にまで影響します。特に幼児期は、親の関わり方ひとつで子どもの自己肯定感が大きく変わります。甘く考えず、意識的に取り組む必要があります。以下の4つを押さえてください。
比べないで「その子のペース」を尊重する
「○○ちゃんはできるのに」と比べるのは最悪です。子どもはすぐに「自分は劣っている」と感じ取ります。成長スピードは人それぞれなのに、親が周囲と比べ続ける限り、子どもは自分に自信を持てません。
昨日よりできたこと、ほんの小さな進歩を見逃さず、大げさなくらいに一緒に喜ぶ。これを徹底できない親は、子どもの心をむしろ削ってしまうことを自覚すべきです。
小さな成功体験を積ませる
自己肯定感を育てる最も強力な材料は「できた!」という体験です。小さなことでいい、必ず達成できる課題を積ませましょう。
たとえば、3歳の子どもが自分でトイレに行けたら徹底的に褒める。自分でカバンを背負ったらその場で拍手する。周囲の大人が一丸となって認めることで、子どもは「自分はできる」と信じられるようになります。
逆に、成功体験を与えられなかった子は、自分から挑戦しなくなり、「できないからやらない」という悪循環に陥ります。
長所を伸ばして“強み”を意識させる
早生まれの子は、劣等感を持ちやすい一方で、柔軟性や協調性といった強みを身につけやすい傾向があります。そこを見逃してはいけません。
私の息子は3歳の時、私が腹痛で苦しんでいるとお腹をさすってくれました。これはまさに「思いやり」という強みです。その瞬間に「優しいね、ありがとう」と具体的に言葉にすることで、子どもは「自分の良さ」を意識できます。
強みを親が言葉で認めなければ、せっかくの長所も埋もれてしまいます。
親が「安心基地」になる
子どもにとって親は“最後の砦”です。どんなにできなくても、挑戦した過程を見て受け止める存在でなければなりません。
「できないことに悔し涙を流す」そんな時こそ、結果ではなく挑戦そのものもフォーカスしてください。親が「大丈夫、ちゃんと見ているよ」と伝えることで、家庭が子どもにとっての安全基地になります。
逆にここを怠れば、子どもは外で傷ついても戻る場所を失い、自己否定を深めてしまうでしょう。
まとめ|早生まれが不利かは育て方次第
早生まれの子は周囲と比べて劣等感を抱きやすいですが、それを放置するのは子どもの成長にとって大きな損失です。親の声かけ一つで、自己肯定感は大きくも小さくも変わります。それほど親の影響力は絶大です。
今回紹介した育て方を実践し、子どもが自分を誇れるようにサポートしてください。親がしっかり寄り添うことで、早生まれの子どもはそのハンデを強みに変え、大きく飛躍できるのです。



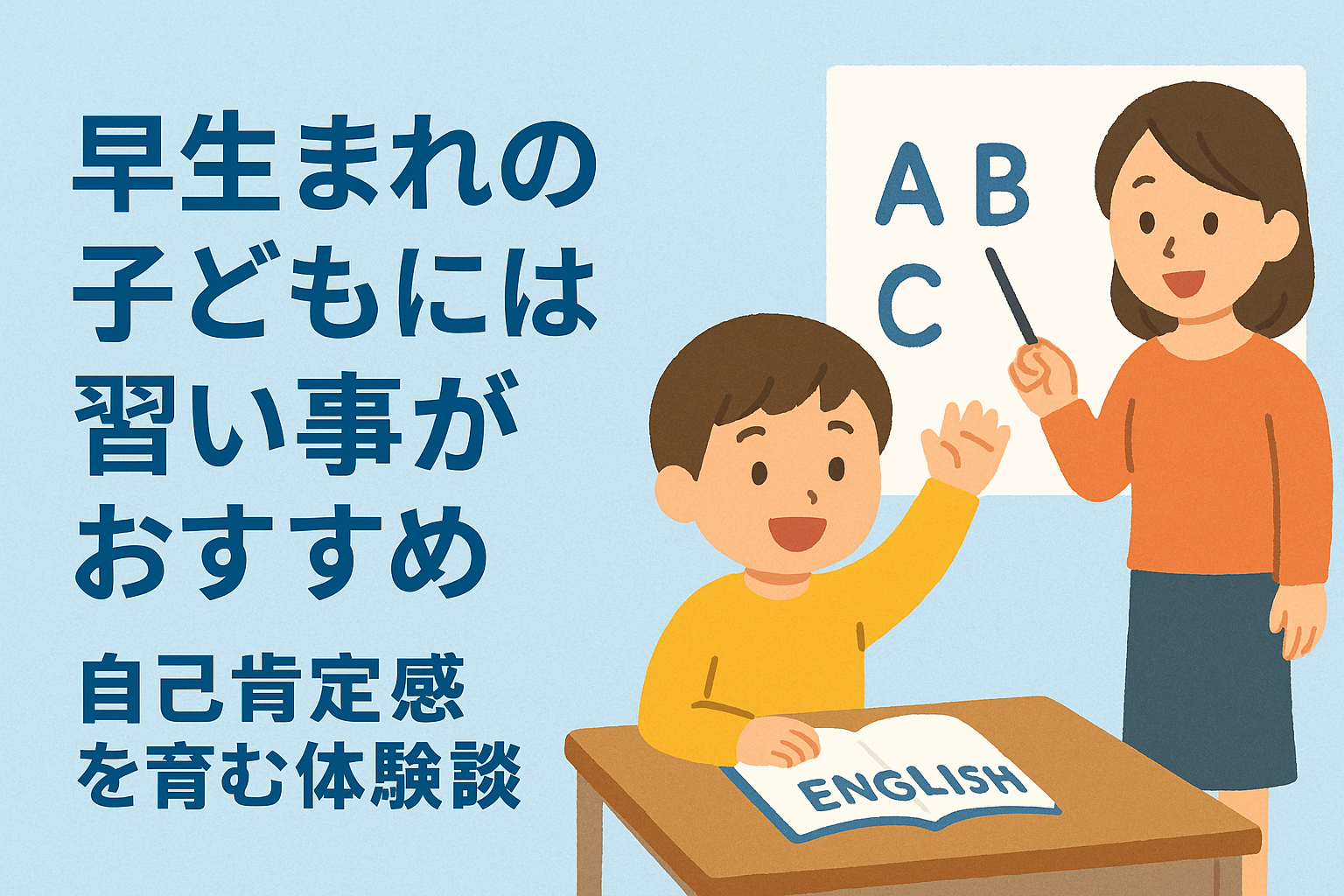
コメント