「早生まれ=不利」というイメージを持つ人は多いのではないでしょうか。確かに早生まれは、遅生まれに比べて脳や体の発達が遅れ、子どもの頃に劣等感を抱きやすいことが特徴です。私自身もその一人でした。けれど、長い目で見れば早生まれだからこその大きなメリットが数多くあるのも事実です。むしろ出遅れた分、努力を覚え、遅生まれよりも成長の幅が大きくなることさえあります。今回は、私の実体験を踏まえながら「早生まれのメリット」を5つ紹介します。劣等感で悩んでいる方こそ、この記事をきっかけに前向きな視点を持っていただければと思います。
早生まれとは?1月1日~4月1日生まれた人を指す
「早生まれ」とは、1月1日から4月1日までに生まれた人を指します。
同じ学年の子どもたちの中でも、生まれてから入園・入学までの期間が短いため「早い生まれ」と表現されるのです。逆に4月2日から12月31日生まれは「遅生まれ」と呼ばれます。
4月1日生まれと2日生まれで学年が変わるのはなぜ?
「年度の始まりは4月1日なのに、なぜ早生まれの区切りは3月31日ではなく4月1日なのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。答えは学校教育法にあります。
学校教育法で定められた「学齢の決まり」
学校教育法では、次のように規定されています。
「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」
ここで重要なのは「満年齢」の数え方です。日本の法律では、誕生日の前日が「満〇歳に達する日」とされます。
- 3月31日生まれ → 3月30日に満6歳
- 4月1日生まれ → 3月31日に満6歳
- 4月2日生まれ → 4月1日に満6歳
つまり、学校が始まる4月1日時点で「4月1日生まれの子はすでに満6歳」「4月2日生まれの子はその日ちょうど満6歳になったばかり」という違いが生じます。
その結果、4月1日生まれは同学年に含まれ、4月2日生まれは翌年度扱いとなるのです。
引用:4. 4月1日生まれの児童生徒の学年について:文部科学省
早生まれのメリット5選
脳が若いうちに教育を受けられる
脳は若いほど柔軟で、教育によって大きく変化します。早生まれの子どもは、同学年の中でもより若い時期に教育を受けるため、脳の可塑性が高い段階で刺激を受けやすいと言われています。その結果、学力が伸びやすい可能性もあるのです。
引用:【早生まれの不利は〇〇で9割解決できる】16万人のMRIを見た脳科学者が解明/子どもの潜在能力を引き出す方法/知能は遺伝より後天的な努力で決まる/早生まれの受験戦略【教育新常識】 – YouTube
遅生まれの友達から刺激を貰える
早生まれは、どうしても同級生より体格や発達で差を感じがちです。私自身、幼稚園~小学校低学年の頃までは「みんなはできるのに、自分はできない」と劣等感を抱いていました。ですが今振り返ると、年上の同級生がいたからこそ刺激を強く受け続け追いつきたいと努力できたのだと思います。
追いつく経験が自信につながる
努力して追いついた経験は、後の大きな自信になります。私の場合は、小学1年生から続けていたバスケットボールがその体験でした。最初は体格差で不利を感じていましたが、小学5年生頃から急に上達が認められるようになり、周囲にも「うまい」と言われる存在になれました。その成功体験が「自分もやればできる」という自己肯定感を育ててくれたのです。
社会性や適応力が身につきやすい
早生まれの子どもは、常に年上の同級生に囲まれるため、自然と協調性や共感力が求められる環境に置かれます。もちろん幼少期は「体力面や理解のスピードで遅れを感じる」こともあり、私自身も集団行動が苦手で劣等感を抱いた時期がありました。しかし、その分まわりに合わせようと努力する過程で、相手の気持ちをくみ取り、自分の立ち位置を考える力が磨かれていったのです。結果として社会人になってからは、コミュニケーション力や適応力が強みとなり、人間関係で大きな壁にぶつかることはほとんどありません。
生涯賃金が増える
多くの企業では、4月に新卒で入社し、60歳の誕生日月に定年を迎えます。早生まれはその分同学年に比べて定年までの期間が一年近く遅い為、その分生涯賃金が増える傾向になります。
早生まれである私自身の体験談
幼稚園〜小学4年生
私は1月生まれで、幼い頃は同級生に比べて発達や成長が遅く感じられました。特に幼稚園から小学校低学年までは、集団行動や友達づくりが苦手で「自分だけできない」という場面が多かったのです。そのため劣等感に包まれ、自己肯定感も低いまま過ごしていた記憶があります。
小学5年生〜高校生
状況が変わったのは小学5年生頃です。1年生から続けていたバスケットボールで周囲に追いつき、むしろ上達が認められるようになりました。苦手な勉強には劣等感を持ち続けていましたが、「バスケなら負けない」という柱ができたことで、自己肯定感を少しずつ取り戻していきました。高校生では学業面でもクラスのトップに入りさらに自己肯定感を高めていきました。
社会人になってから
社会人になってからは、早生まれを不利に感じることはありません。むしろ、子ども時代に味わった劣等感や「追いつこう」と努力した経験が、今では仕事の強みに変わっています。周囲に遅れをとっても粘り強く取り組む姿勢は、仕事を進めていくうえでも私の武器となりました。さらに、同学年の中で一番若いという事実は、年齢的にも気持ちの面でもプラスに働いています。早生まれで苦労した経験は、大人になって確かな財産になっているのです。
まとめ|早生まれは可能性に満ちている
早生まれは幼少期からどうしても劣等感を抱きやすい立場にあります。体格や発達の差で苦労することは事実です。しかし、長期的に見ればその経験が確かな強みに変わります。改めてメリットを整理しましょう。
- 脳が若いうちに教育を受けられる
- 遅生まれの同級生から刺激を受けられる
- 努力して追いついた経験が自信になる
- 社会性や適応力が鍛えられる
- 定年まで働ける期間が長く、生涯賃金も増える
早生まれは「不利」ではなく「伸びしろが大きい環境」に置かれているということです。子ども時代に一歩遅れをとった分だけ、追いつき、追い越すチャンスがあります。もし早生まれを理由に自分を否定しているなら、それは単なる思い込みです。むしろ誇るべき特性を持っているのです。少数派である早生まれに生まれたからこそ、その経験を糧に、堂々と前向きに生きていきましょう。


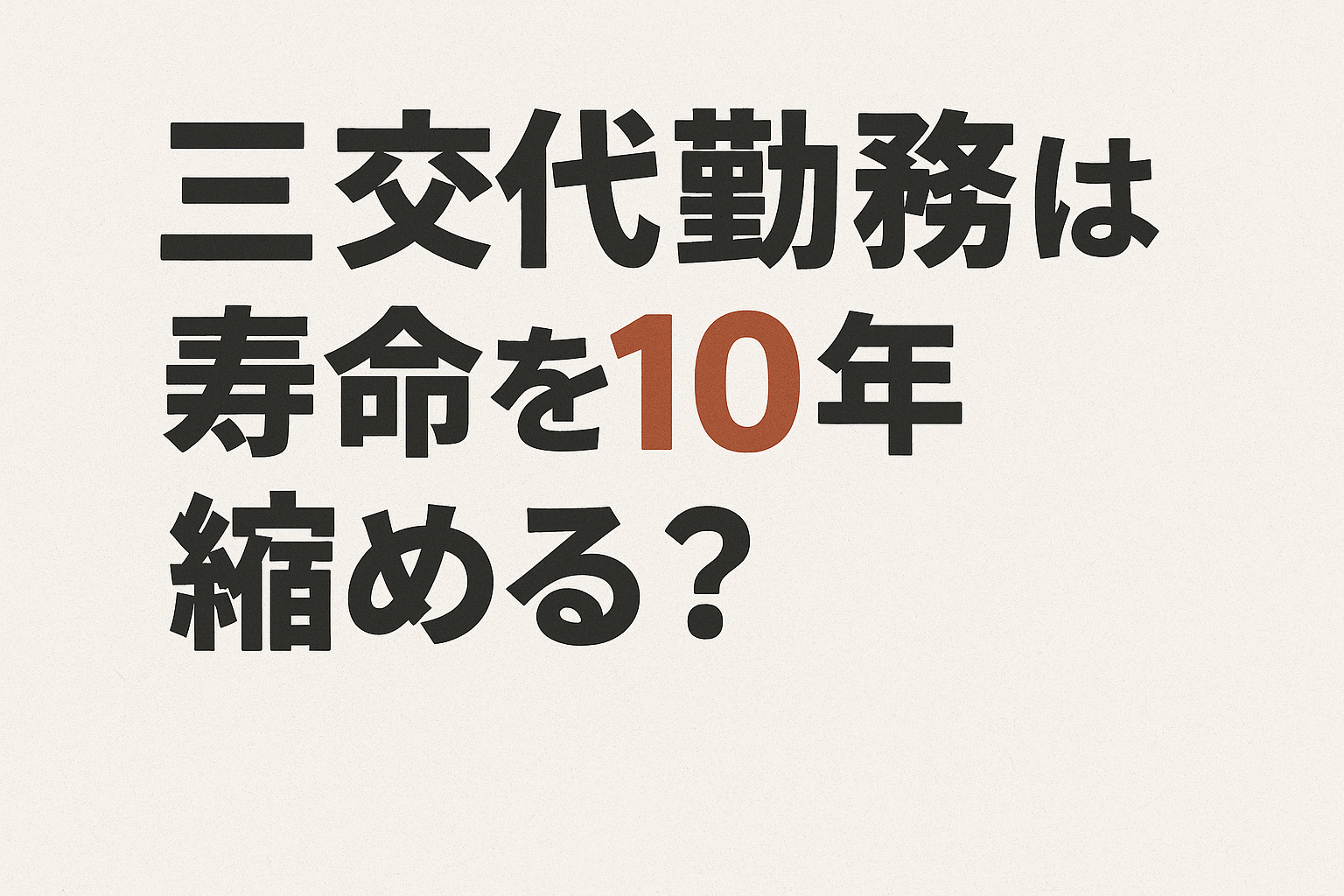

コメント