私はまだ29歳です。
それでも、ふとした瞬間に「死」への恐怖を感じることがあります。
昔からそうでした。夜中に目が覚めたときや、一人でぼーっとしているとき。突然、「いつか自分はこの世からいなくなるんだ」と気づいて、ゾッとすることがあるんです。
最近、同じ歳の実業家が亡くなったというニュースを見ました。どこか他人事ではない感覚があり、それがきっかけで、ますます死について考える時間が増えました。
死ぬことは、まだまだ先の話だと思っています。けれど、年を重ねるごとに「死」に向かって着実に近づいている。その事実に、心のどこかで怯えながら生きているのもまた、確かです。
今回は、そんな私自身の思いや体験をもとに、「死の恐怖」とどう向き合っていけばいいのかを、一緒に考えてみたいと思います。
その「怖さ」は自然なこと
死への恐怖は、人間にとってごく自然な感情です。
そもそも人間という生き物は、生き延びることを最優先に行動するため、死という未知の状態に対して本能的に警戒心を抱くようにできています。
この恐怖は、危険な状況から身を守るために必要な反応でもあります。外敵から逃げたり、リスクを避けたりする力の源が「死への恐れ」なのです。
ただ、人間は思考力が発達している分、本能以上の不安を抱きます。
未来を想像し、過去を振り返ることができるからこそ、「死」という漠然としたものに対して、複雑な恐怖を感じてしまうのです。
「いつか必ず死ぬ」と理解した瞬間に、感情的な反応としての恐怖が生まれる──
それは、とても人間らしい、自然なことなのだと思います。
死を考えるときに湧いてくる不安とは?
- やり残したことへの後悔
3年前、コロナの予防接種を受けたときのことです。
副作用で高熱が出て、夢の中でうなされながら「やばい、死ぬかも…」と本気で思ったことを、今でもよく覚えています。
そのとき、頭の中には人生への後悔のようなものが、どっと押し寄せてきました。
「まだやりたいことがある」「子どももまだ小さいし、これから楽しい人生が待っているはずなのに」──そんな未練が、まるで走馬灯のように浮かんできたのです。
遠い存在だった「死」が突然目の前に立ちはだかったとき、人はまず「恐怖」よりも「後悔」を感じるのかもしれません。
- 家族を残していくことの心配
もし今、自分に何かあったら──
子どもや妻はどれほど悲しい思いをするだろう。
そして、その後の生活はどうなるのだろうか。そう考えると、不安でなりません。
私は化学工場で働いています。
その仕事は、常に危険と隣り合わせです。爆発のリスク、転落事故、酸欠、化学物質による中毒……。
「無事に家に帰れる」ことが決して当たり前ではない仕事です。
だからこそ、もっと強く自覚を持たなければならないと思っています。
自分の命は、自分ひとりのものではなくなった今──
家族を守るためにも、日々の仕事に対する危機感と緊張感を忘れてはいけないと感じています。
- 死後がどうなっているのか分からない恐怖
死んだあと、人はどこに行くのか。
無になるのか、それとも何かがあるのか──それは誰にもわかりません。
この「分からなさ」が、死に対する一番の恐怖なのかもしれません。
もしかしたら、恐ろしい場所ではなく、意外と穏やかで楽しいところかもしれない。
でも確信は持てない。その“不確かさ”が、どうしようもない不安を生むのです。
時々、死期が近いはずのおじいさんやおばあさんは、何を考えているのだろう?
死ぬこと、先が長くないことが怖くないのかな?と考えることがあります。
特に、笑顔で穏やかに過ごしている高齢者を見ると、「年を取れば死への恐怖も薄れていくのかも」と、子どもの頃はなんとなく思っていました。
でも、いざ大人になってみると……実際は違いました。
むしろ、子どもの頃より今のほうが、死が怖いと感じる自分がいます。
大切な人が増え、守りたいものが増えたからなのか。
それとも、「無」や「消えること」の意味を、少しずつ理解してきたからなのか──。
死後がどうなるのか分からないという事実は、私たちにとって本質的な不安として、残り続けるのだと思います。
「意味のある人生だったのか?」という問い
人は、生きがいがないと生きていけない生き物だと思います。
それは仕事かもしれないし、趣味や友人、家族との時間かもしれません。
つまり、「生きる意味」は人それぞれであり、正解はひとつではない。
だからこそ、生きがいを感じながら日々を過ごせているなら、それだけで十分価値のある人生だと思います。
私たちは、何かに夢中になっているとき、死のことなんてあまり考えません。
つまり、生きがいがあるからこそ、前を向いて生きていける。
そしてその積み重ねが、「意味のある人生だった」と感じられるものに変わっていくのではないでしょうか。
たとえ大きな功績を残せなくても、誰かに何かを渡せたなら、それでいい。
子どもに受け継いだ優しさ、誰かにかけたひとこと、共に過ごした時間──
そうした小さなものが、人生の意味を形づくっていくのだと思います。
結び:いつか終わるからこそ、「今日」を生きよう
家族や近しい人が亡くなったとき、私たちは強く「死」を意識し、恐怖を覚えます。
けれど、数日が経つと、また日常へと戻っていきます。
それは、忘れるからではなく、引きずらずに生きていく力が人間にはあるから。
だからこそ、私たちは「今日」という日を生きていけるのだと思います。
「今日が人生で一番若い日」とよく言われます。
まさにその通りで、若いということは、選択肢がたくさんあるということ。
どの道を選んでも、自分が納得できるなら、それは正解の道に変わっていきます。
死への恐怖が完全になくなることは、きっとありません。
でも、「どう生きたいか」に意識を向ければ、少しずつ恐怖は小さくなり、
代わりに「生きている時間の価値」が大きくなっていくはずです。
終わりがあるからこそ、「今」が尊くて、かけがえのないものになる──
そんなふうに思える生き方を、これからもしていきたいと思います。

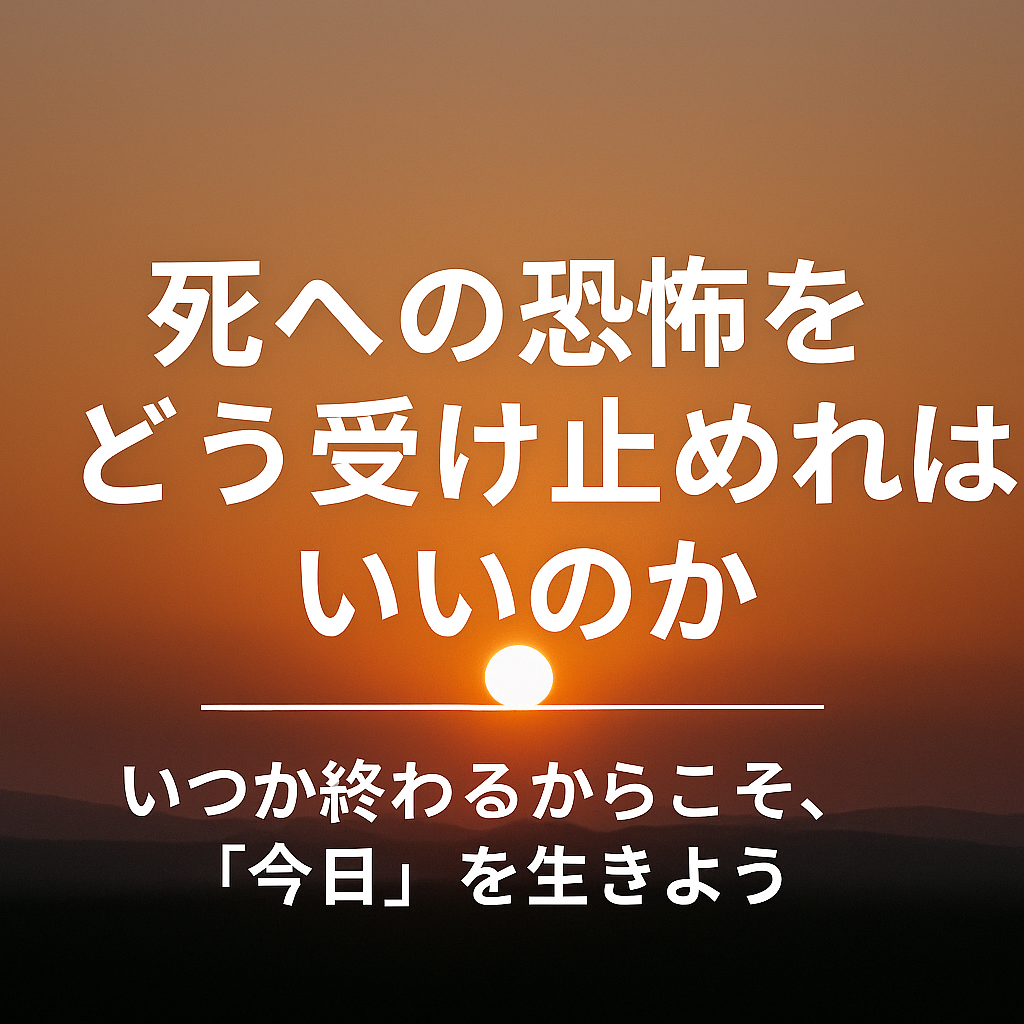

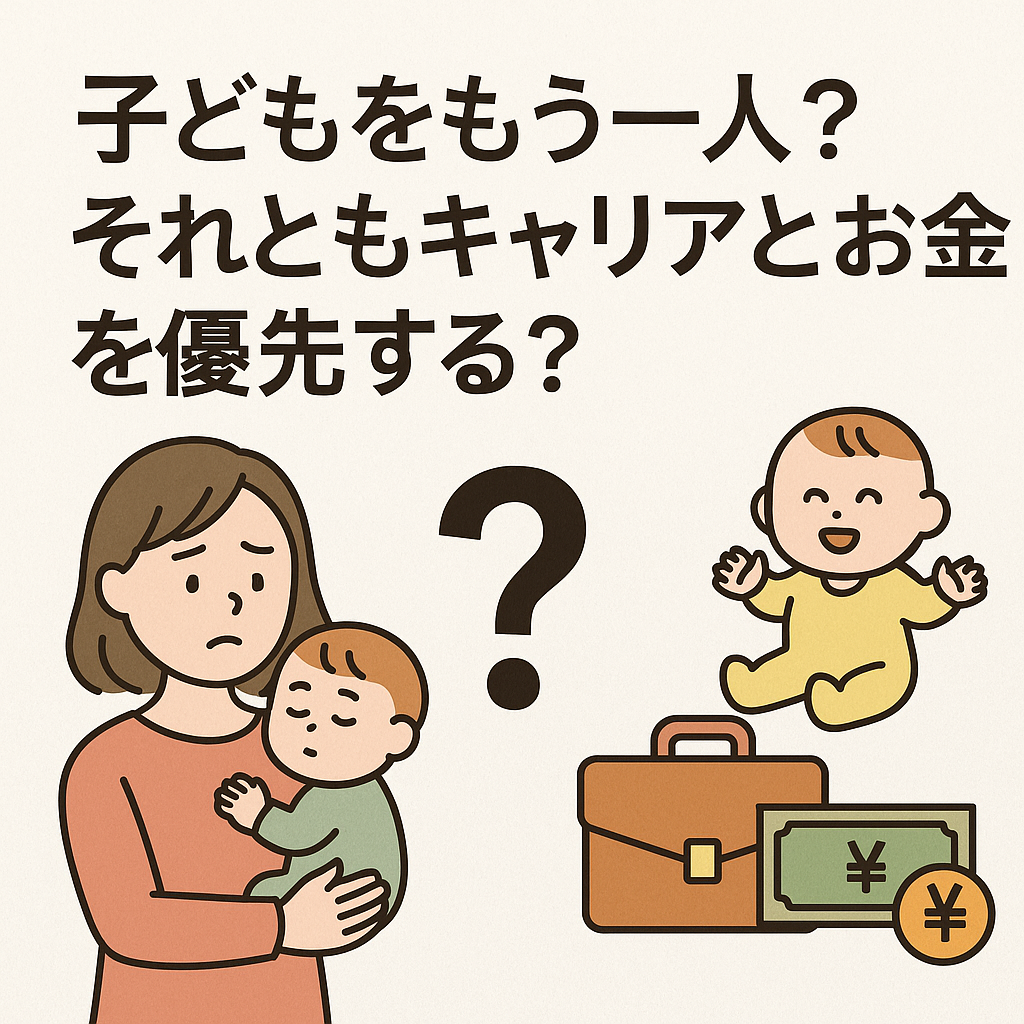
コメント