1. はじめに|夜勤あり共働き、しかも子育て中…その大変さとは?
夜勤勤務は、それだけでも心身ともにハードなものです。
そこに「共働き」や「子育て」が加わり、すべてを両立するのは本当に大変。
独身の頃は、好きなタイミングで寝て、好きなタイミングでご飯を食べる…そんな自由な生活ができていました。
しかし、結婚や出産を経てライフスタイルは一変。家族の生活リズムに合わせて動く必要があり、自分の時間はほとんどゼロに。
さらに、年齢を重ねるごとに体力の衰えを感じることも増え、「こんな生活いつまで続けられるのかな」と不安になることもあるのではないでしょうか。
この記事では、そんな「夜勤あり共働き、しかも子育て中」という限界ギリギリの毎日を、少しでもラクにするための過ごし方や工夫を、実体験をもとに紹介していきます。
2. 家族のスケジュールはどう回す?夜勤・子育て家庭の1日モデル
● 夜勤明け〜夜勤までの流れ
夜勤が朝8時に終わって帰宅すると、すぐに子どもの保育園の送迎が待っています。
保育園の開始時間に合わせなければならないので、ゆっくりする間もありません。しかも、子どもが思うように動いてくれない日もあって、朝からイライラ…結局、泣きながら遅刻、なんてことも正直あります。
送迎が終われば、ようやく一息。といっても、自分の時間=寝る時間。
だいたい10時頃から16時頃まで仮眠を取り、そこから夕食の準備と保育園のお迎えが待っています。その後はお風呂、寝かしつけ…そして、再び夜勤へ。まさに休む暇のない毎日です。
● パートナーとの役割分担はどうする?
この生活を回すには、パートナーとの連携が不可欠です。
とはいえ、交代勤務だと曜日や時間で家事・育児の担当を固定するのは難しいのが現実。
私たちは、まず最低限必要なタスクを洗い出して分担を考えました。
たとえば、以下のような家事・育児のタスクがあります:
- 子どもの送迎
- 食事の準備
- 洗い物
- 洗濯
- 子どものお風呂
中でも私が一番しんどいのは「食事の準備」と「子どものお風呂」。
食事はヨシケイを導入したことでかなり時短&ラクになりました。
お風呂に関しては、子どもに「お風呂入ったらスイカ食べようね」と、ご褒美を提案することでスムーズにお風呂に入る日もあります(もちろん毎回うまくいくわけではありませんが…)。
● 子どもの生活リズムを崩さない工夫
夜勤勤務だと自分のリズムが不規則になる分、子どもの生活リズムを守ることを意識しています。
我が家では「毎日21時には寝る」というルールを徹底しています。
夜勤の日でも子どもをその時間に寝かしつけることで、体内時計を乱さずにすみます。
また、私自身も21時からの1時間ほど一緒に仮眠をとることで、夜勤前にリフレッシュする時間を確保しています。
3. 家事と育児を“仕組み化”でラクにするコツ
● ごはん・洗濯・掃除…「やること」を減らすという考え方
共働きで夜勤もある生活では、とにかく「やらないことを決める」のが大事です。
我が家では以下のように、家事をできるだけ「仕組み化」して毎日の負担を減らしています。
- ごはん作り:ミールキットの「ヨシケイ」を活用。献立を考える必要がなく、調理も15〜20分で完了。料理のハードルがぐっと下がりました。
- 洗濯:ドラム式洗濯乾燥機を導入したことで、洗って干して…という手間が大幅に削減。夜勤明けでもストレスなく回せます。※リンクはアフィリエイトを含みます
東芝 TOSHIBA ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 洗濯12.0kg 乾燥7.0kg 右開き ボルドーブラウン TW-127XP4R-T (大型配送対象商品 / 配達日・時間指定不可/ 沖縄および離島対応不可)〈TW127XP4R-T〉 - 掃除:毎日掃除機をかけるのは正直ムリなので、水回り(台所・洗面所・トイレ)だけは「毎日きれいに保つ」ことに集中。床掃除は時間のある日にまとめて。
このように「やらなきゃ」を減らす工夫をするだけで、精神的な余裕も生まれます。
● 作り置きやミールキットで調理時間を時短
時間に余裕がある週末には、冷凍保存できる簡単な作り置きおかずを数品用意しておくと、平日の自炊がグッとラクになります。
ただし、「週末すらゆっくりできない…」という方には、やっぱりミールキットの活用が現実的な選択肢です。
たとえば、我が家でも使っているヨシケイには、こんなメリットがあります:
- 毎日違うメニューが届くので献立を考える手間がゼロ
- 子どもでも食べやすい、やさしい味付けのメニューが豊富
- 食材は使い切りサイズなのでムダが出にくい
さらに、冷凍食品やカット野菜なども積極的に取り入れて、“罪悪感のない時短”を意識しています。こうしたアイテムをうまく使えば、「もうご飯作りたくない…」という日でも、乗り切れる可能性が高まります。
そして、ヨシケイを使っていて感じる一番のメリットは、いろいろな料理を家族にふるまえることです。
「このメニュー、子どもが意外と好きなんだな」
「これは夫(妻)に好評だった」
…そんな新しい発見があるのも嬉しいポイントです。
気に入った献立は自分のレシピノートとして残しておくのもおすすめです。時間に余裕があるときにもう一度作れるし、料理のレパートリーも自然と広がっていきます。
4. 睡眠時間の確保がカギ!夜勤後でもしっかり休むために
● 家族に「寝る時間」を理解してもらう工夫
夜勤を経験したことがないパートナーや家族にとって、夜勤のつらさはなかなか想像しにくいもの。
「朝10時から16時まで寝てるなら元気なんじゃない?」と思われることもあるかもしれません。
でも実際は、昼間の睡眠は質が落ちやすく、思ったより回復できないんですよね。
だからこそ、ただ「疲れてるから休ませて!」ではなく、
「洗い物はやっておくから、20時から22時だけは寝かせてほしい」
「ママもしんどいよね。でも、この時間だけは静かに過ごさせてくれると助かる」
といった思いやりのある伝え方を意識することが大切です。
一方的に頼むのではなく、お互いの大変さを尊重しながら調整していくのがポイント。
● 遮光カーテンや耳栓など、睡眠環境の見直し
日中は明るいし、車の音や近所の工事など、騒音にも悩まされやすい時間帯。
そんなときは、睡眠の質を上げるためのグッズを取り入れるのも効果的です。
- 遮光カーテン
- 耳栓
- アイマスク ※リンクはアフィリエイトを含みます
3D スリープ アイマスク Eye Air 楽天1位! 遮光 遮光性抜群 アイピロー 安眠 睡眠 快眠 就寝 リラックス リフレッシュ 温感 疲れ目 目元ケア マツエク まつエク 旅行 移動 健康 洗濯OK ホット トラベルグッズ MYTREX マイトレックス アイエアー ギフト クリスマス
私の場合は、夜勤明けは眠気MAXでわりとすぐ寝られますが、それでも環境が整っていると深く眠れる感じがします。
ちょっとしたアイテムでも、回復度が違ってくるので、自分に合った方法を見つけてみてください。
● 短時間でも質を高める“夜勤の仮眠テクニック”
夜勤中、特に眠気がピークになるのは朝4時〜6時頃。
この時間帯に強烈な眠気を感じる方も多いと思います。
そんなときは、休憩時間を活用した“短時間仮眠”がおすすめ。
- デスクにうつ伏せで20分だけ目を閉じる
- スマホのアラームをセットして寝過ぎ防止
- 深く寝すぎないことで、起きた後のだるさも回避
20分前後の仮眠でも、頭がスッキリして集中力が回復します。
「仮眠なんて無理」と思う方でも、一度試してみる価値はありますよ。
5. 夫婦のすれ違いを防ぐコミュニケーション術
● LINEや家族カレンダーの活用で“会えない日”もつながる
夜勤のある生活では、家族と顔を合わせる時間が限られます。
日によっては「夜しか会わない」「全く会えない」ということも。
そんなときこそ、LINEや家族カレンダーアプリの活用が大切です。
- 今日の出来事や子どもの様子をLINEで共有
- 家族カレンダーに夜勤の予定や送り迎えの担当などを記録
- 「あとで話したいことあるよ」と前もって一言伝えておく
たとえば、子どもが寝たあとにゆっくり話したいことがあるときは、
「今日の夜、少しだけ話せる?」と一言伝えるだけで、心の準備ができてすれ違いが防げます。
忙しい日々だからこそ、“会えなくてもつながる工夫”が大切です。
● 感情的になる前に「伝える習慣」をつける
夫婦の関係においては、言い方ひとつで空気がピリつくこともあります。
特に、寝不足や疲れがたまっているときは、ちょっとしたことでもイライラしがち。
そんなときは、いったん深呼吸。
感情的になる前に、気持ちを整理する習慣をつけましょう。
- 紙に書き出してみると、意外と冷静になれる
- 「なんで怒ってるんだっけ?」と気づけることもある
- 私の場合は、いったん寝るとだいたいスッキリします(笑)
大事なのは、「イライラしたことをぶつける」のではなく、
「何がイヤだったのか」「どうしてほしかったのか」を冷静に伝えること。
相手に伝える前に自分の心を整えることで、すれ違いが衝突になるのを防ぐことができます。
6. 子育ては一人で抱えない!頼れるサポート活用法
● ファミリーサポート・一時保育の使い方
夜勤勤務の人は日中に少しは自分の時間が取れるかもしれませんが、日勤フルタイムのママやパパは平日は仕事、休日も子どものお世話…というケースも多いですよね。
「一人の時間なんて全然ない」なんて声もよく聞きます。
そんなときに役立つのが、地域のファミリーサポートや一時保育、ベビーシッターサービスなどの支援です。
- 土曜日も預かってくれる保育園は多い
- ファミサポは数時間だけの利用もOK
- 家事代行や民間サービスも、時短・リフレッシュの味方に
「子どもに負担をかけてしまうのでは…」と罪悪感を感じる方もいますが、まずは自分のケアを最優先に考えてください。
子どもは案外たくましく、初めての場所でも元気に遊んでいます。
心配しすぎて疲れるくらいなら、一歩踏み出して“頼る勇気”を持つことが大切です。
● 「甘えること」は悪じゃない
頑張り屋さんほど、「自分がもっとやらなきゃ」「助けを求めるなんて情けない」と思いがちです。
でも、甘えること=悪いことではありません。
- 頭が真っ白になるほど仕事で失敗した日
- 子どもに向き合う気力もわかない日
- 誰かと話すだけで泣きたくなるような日
…そんなときこそ、誰かに頼っていいんです。
毎日頑張っているあなたの姿は、ちゃんと家族も、周囲も見ています。
疲れを感じたときこそ、「一人で抱えない」「助けを求める」ことが、長く育児や仕事を続けていく上で最も大事なスキルなのかもしれません。
7. 自分を大切にするためのメンタル&体調管理法
● 疲れが抜けないときのセルフケア習慣
夜勤と子育て、さらに家事に仕事…。気づけば毎日フル稼働で、「とにかく疲れが取れない…」という日もありますよね。
そんなときは、“がんばる”ではなく、“いたわる”を意識してみてください。
- 朝は白湯を飲んでゆっくりスタート
- 好きな音楽を聴きながらストレッチ
- お風呂にアロマを入れてリラックス
- 10分だけ仮眠 or 目を閉じる時間を取る
- 近くの銭湯でサウナ
大げさなことでなくてOK。小さな習慣の積み重ねが、心と体を回復させる一歩になります。
● 「完璧じゃなくていい」と思える考え方
家事も育児も仕事も、完璧にこなそうとすると心が折れます。
部屋が少し散らかっていたっていい、コンビニご飯の日があったっていい。
「今日はこれだけやれたからOK」と、自分に小さな“合格点”を出してあげる習慣をつけましょう。
理想通りにいかない日があるのは当たり前。
「できたこと」に目を向けることで、メンタルの回復力もグッと上がります。
● 夫婦で“労い合う”ことの大切さ
一番身近な存在だからこそ、夫婦間の「ねぎらいの言葉」はとても大きな意味を持ちます。
- 「いつもありがとう」
- 「疲れてるのに助かったよ」
- 「今日はゆっくりしてね」
そんな一言で救われる気持ち、誰しも経験があるのではないでしょうか?
忙しいからこそ、感謝や思いやりを言葉にする習慣を大切にしたいですね。
8. まとめ|夜勤共働きでも、家族らしく笑顔で過ごすために
● 完璧を目指すより、バランス重視で
夜勤・共働き・育児…どれもエネルギーを使うことばかり。
完璧を目指そうとすると、どこかで無理が出てしまいます。
だからこそ、「今日はここまでできたからOK」と、“ほどよいバランス”を自分の基準で決めることが大切です。
● 「しんどい」と言える環境をつくろう
疲れても、悩んでも、「大丈夫?」って聞いてくれる相手がいると救われますよね。
パートナーや家族、時には職場の同僚など、「しんどい」「つらい」と言える環境づくりを意識しましょう。
それはあなた自身だけでなく、周囲にとっても優しい家庭や職場をつくる第一歩になります。
● 今日からできる一つの工夫を見つけてみよう
たとえば…
- ごはんをヨシケイに変えてみる
- 仮眠用のアイマスクを買ってみる
- 1日1回、パートナーに「ありがとう」を伝える
小さな一歩が、家族みんなの笑顔と心の余裕につながっていきます。
夜勤勤務も大変と思いますが、無理せず、頼りながら、自分を大切にする。そういう暮らしを始めてみませんか?

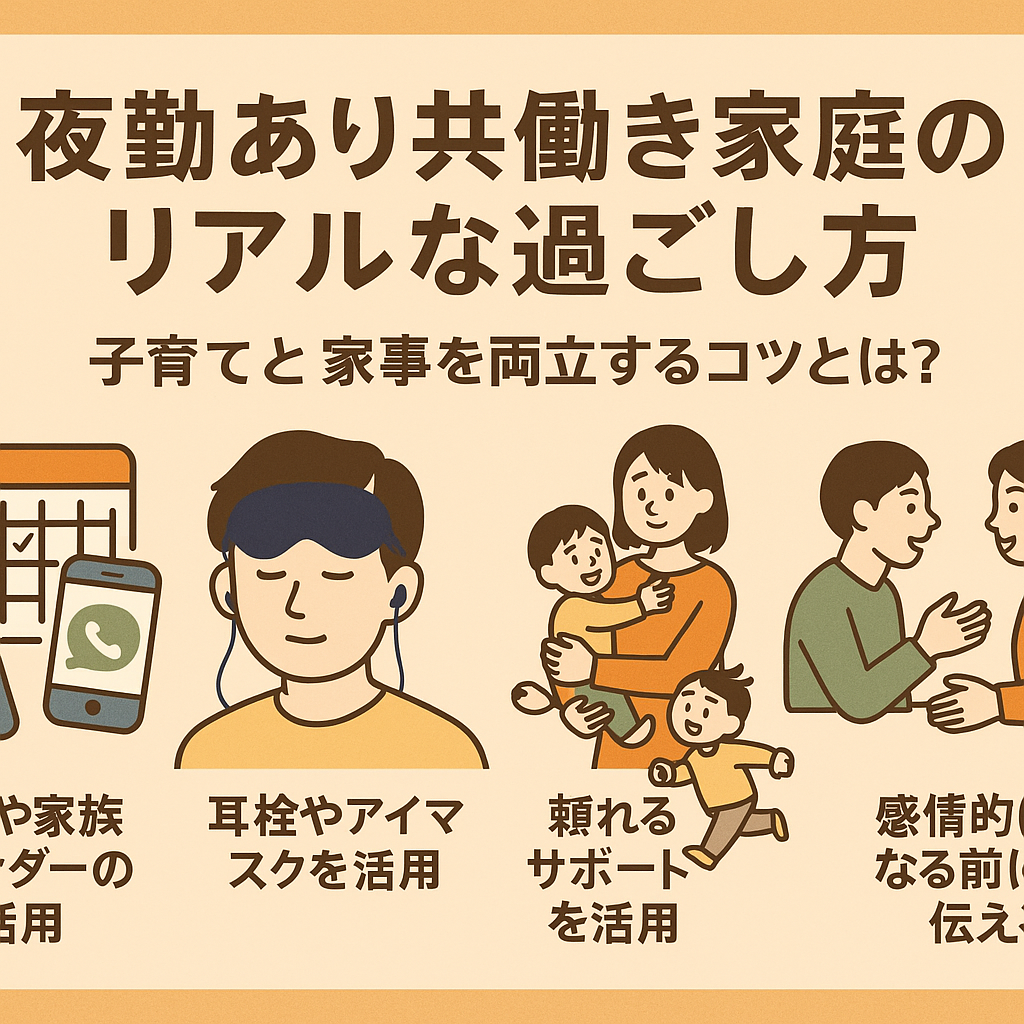
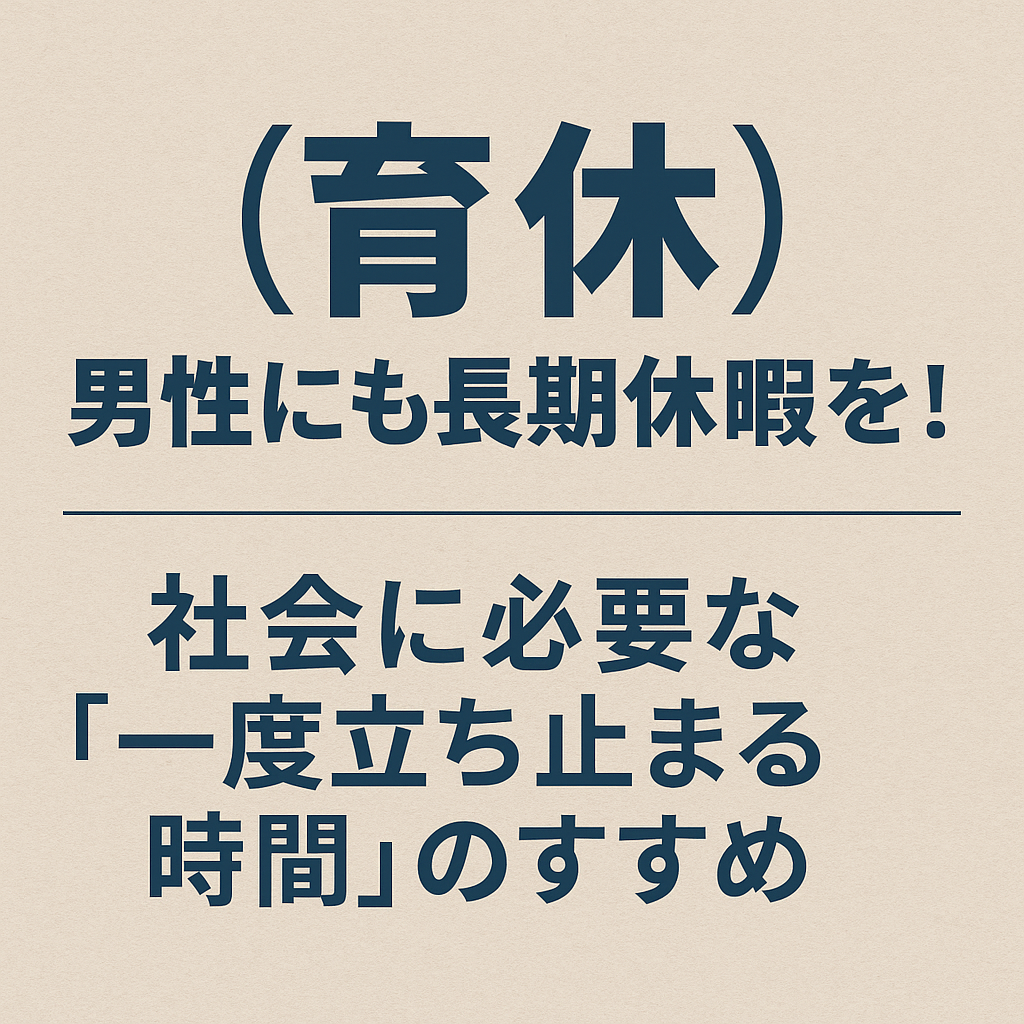

コメント